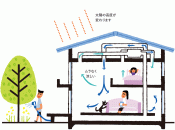*この記事は、「天狼院書店」に掲載された記事を転載したものです。
新築の新居に引っ越してはじめての買い物はコンビニ弁当だった。
それも昼飯でなく、夜ごはんである。
「新居初日の夜は豪勢にスキヤキ、食後にケーキで家族団らんじゃないの?」
いやいや。
大量の荷物を運び込み、キッチンや風呂など設備の説明を受け、電気屋、水道屋の手続きをし、手伝ってくれた友人たちを送り出したら日がもう暮れている。
「ただ空腹が満たればいい」という思いで、最後の気力を振り絞ってコンビニに身体を引きずっていった。……今となっては良い経験。マイホームは“夢”ばかりでないことを悟った日である。
どうして“新築初夜”のことを思い出したのか?それは、この記事を書いている今が12月1日、日曜日だから。
「全然分からない」
という声が聞こえてきそうなのでもう少し説明させてもらうと、私は工務店に勤めていて、毎月第1日曜日は“アフター定期訪問”の日になっている。つまり“夢”だったマイホームを建て、“現実の暮らし”を営むお施主さんと会える日。そんなお施主さんと会うと、半ば強制的に自分の家のことを思い出してしまうのである。
続きを読む