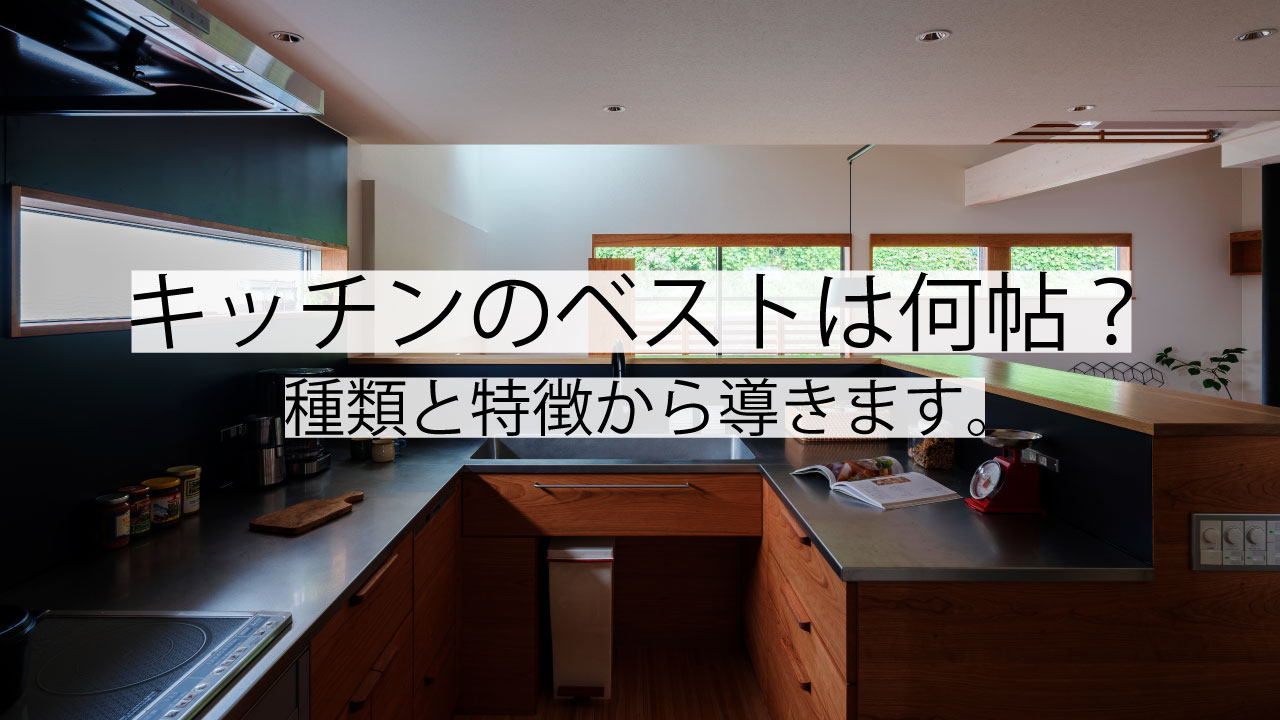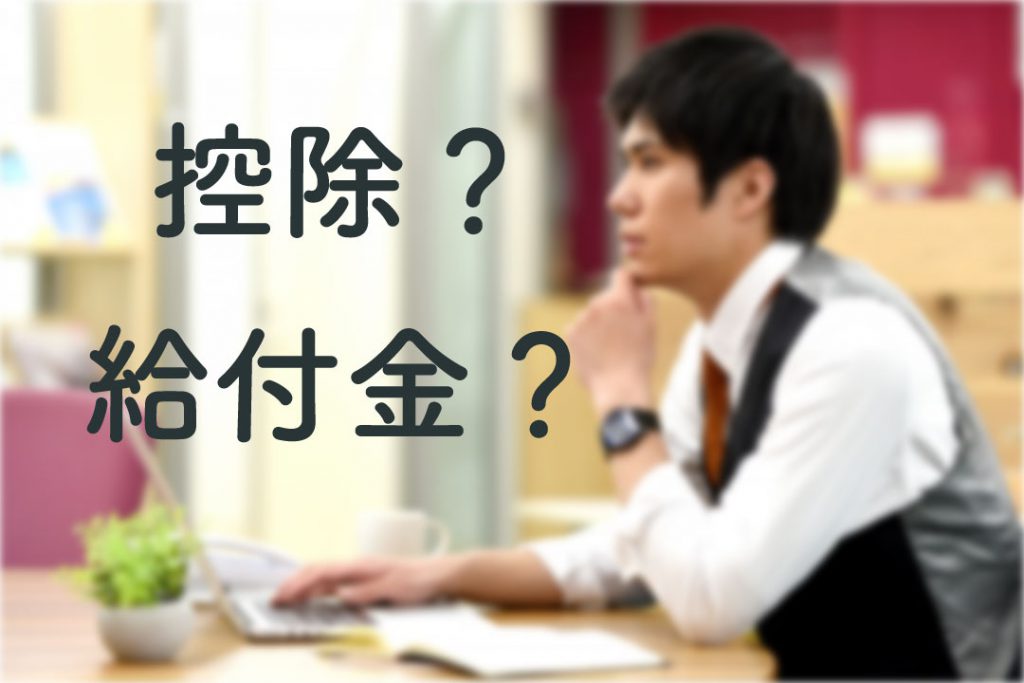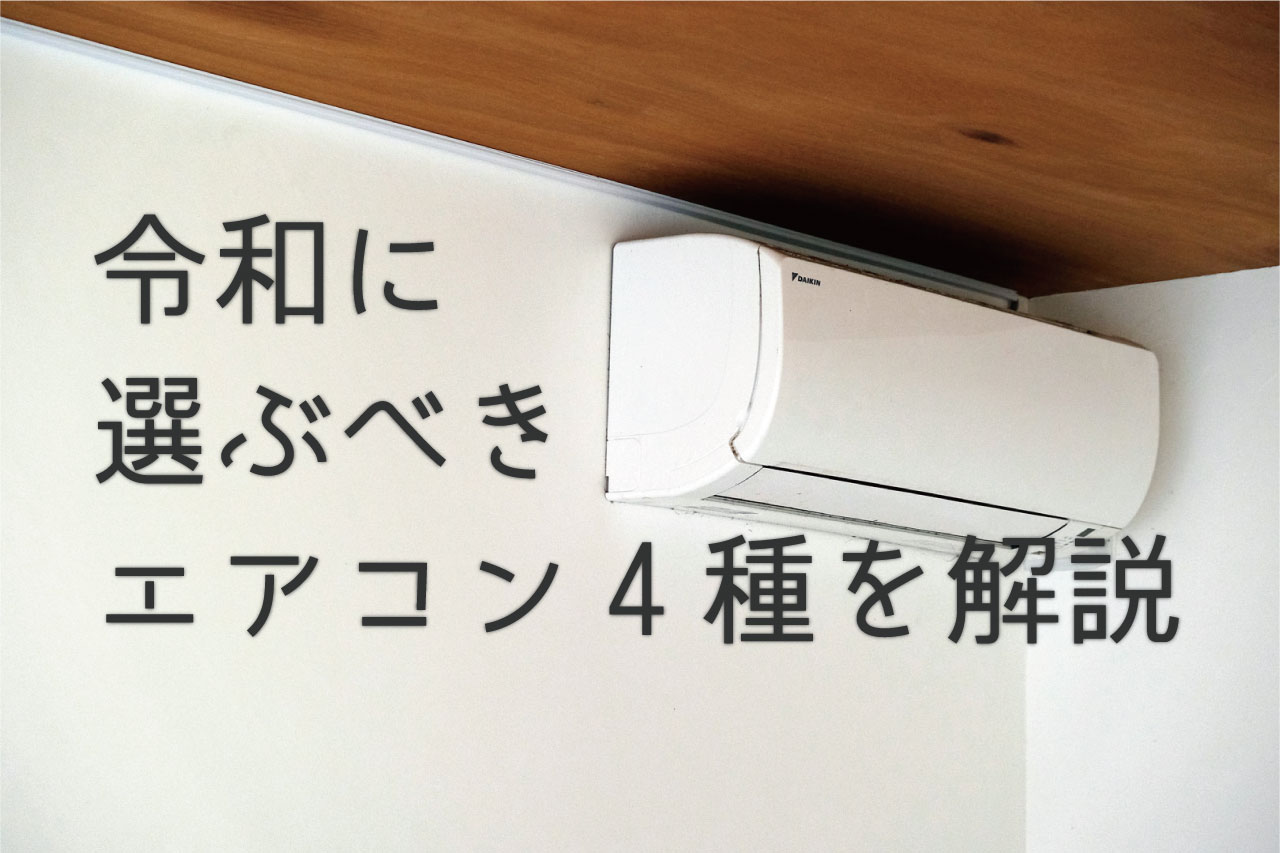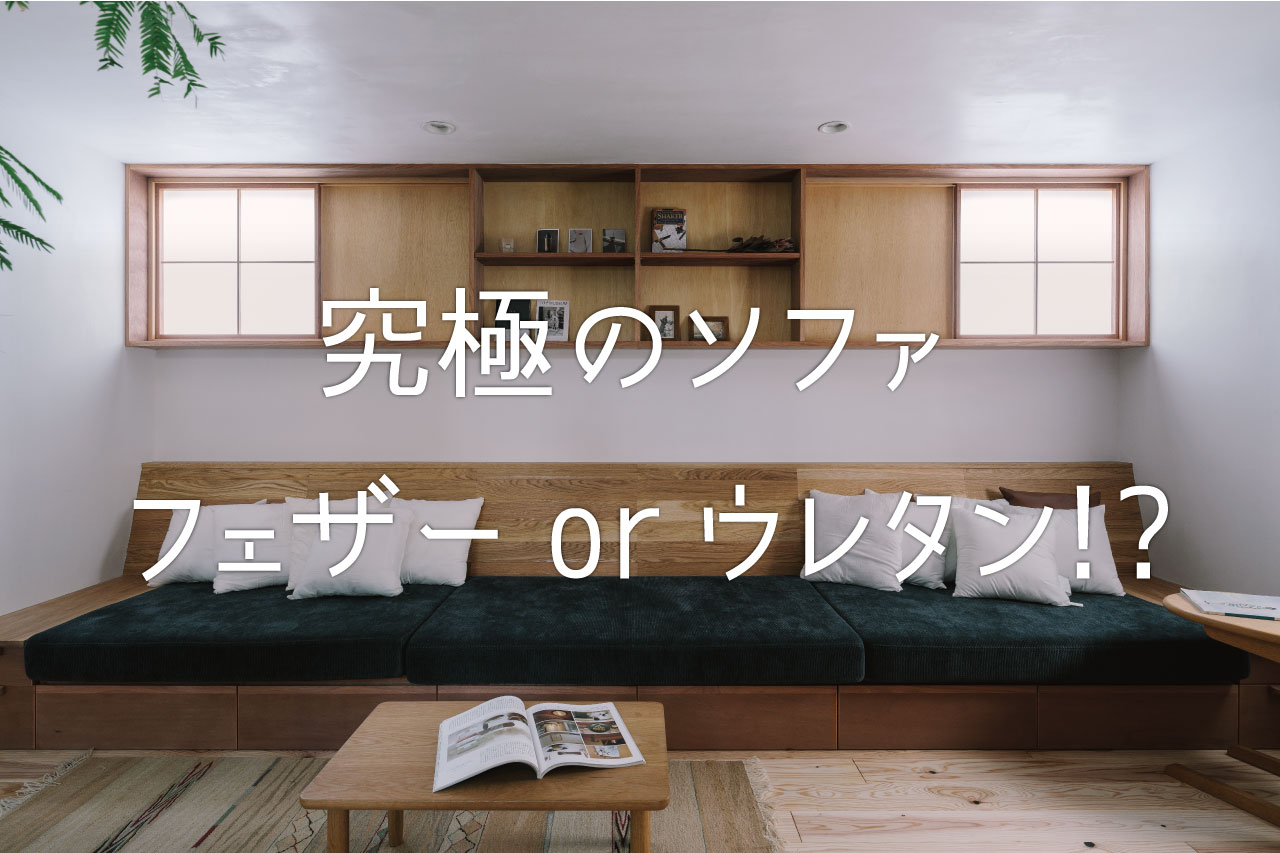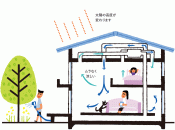新築住宅を考えるとき、多くの人がこだわるのが収納。特に、収納量をボリュームアップさせる傾向があります。しかし、実際に持ち家に感じる不満をリサーチすると、その第1位が「収納の少なさ」だと言われています。
建てる前に検討したにも関わらず、なぜそんなことが起こるのでしょうか? そこで今回は、弊社代表で一級建築士の大迫に「収納の設計の失敗しがちなポイントと、ベストな収納を手に入れる考え方」について聞いてみました。

〈ベガハウス代表・大迫プロフィール〉
1974年鹿児島県鹿児島市生まれ。1995年北九州ポリテクカレッジ卒業。ゼネコン現場監督3年、設計事務所3年を経て、ベガハウス入社。2019年代表取締役社長就任。一級建築士、一級施工管理技士。近著に「暮らしを建てる〜ベガハウスの家づくり〜」
本ブログでは、設計士として多くの家づくりを手がけた経験からたどり着いた「収納の最適量」をはじめ、「ベストな収納方法」「収納力がアップする考え方」など、すっきりとした家で暮らすためのポイントをご紹介します。
続きを読む