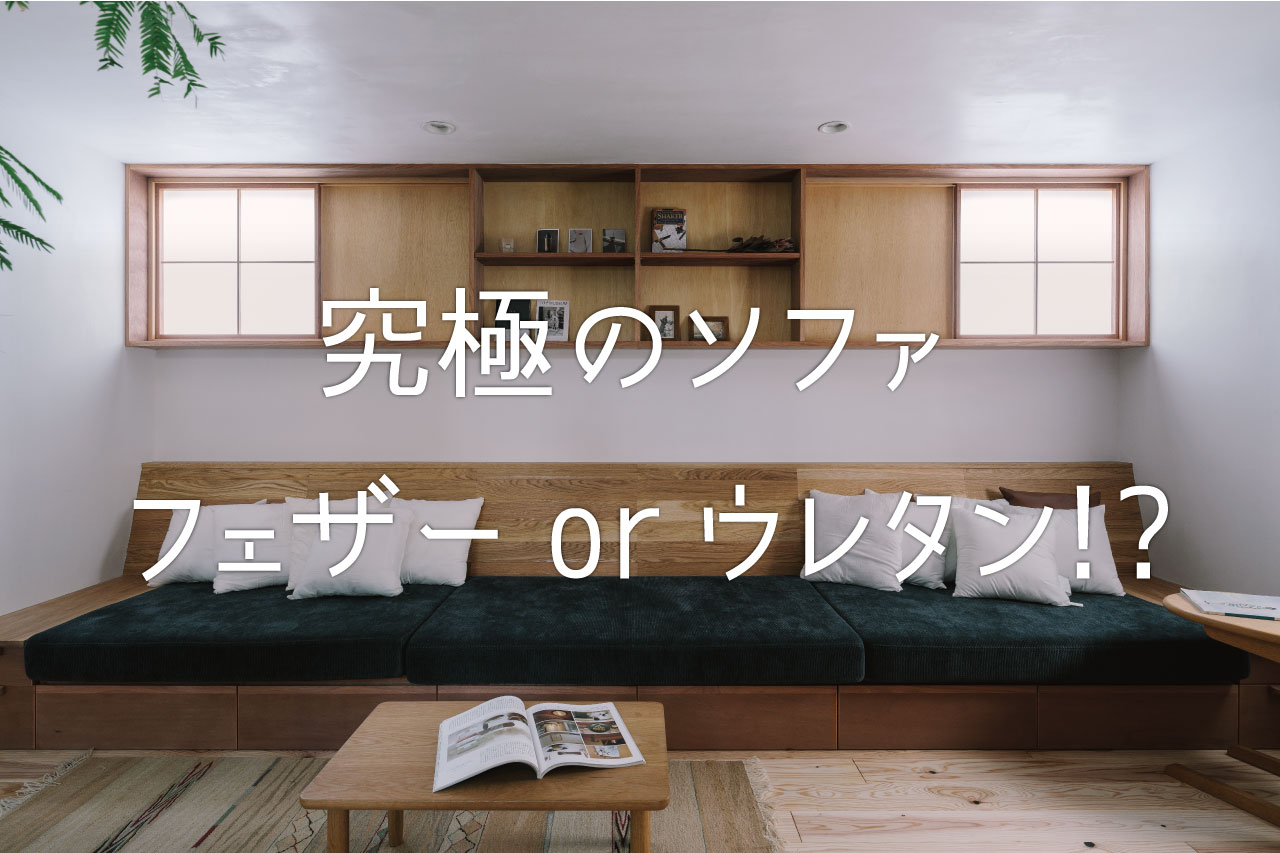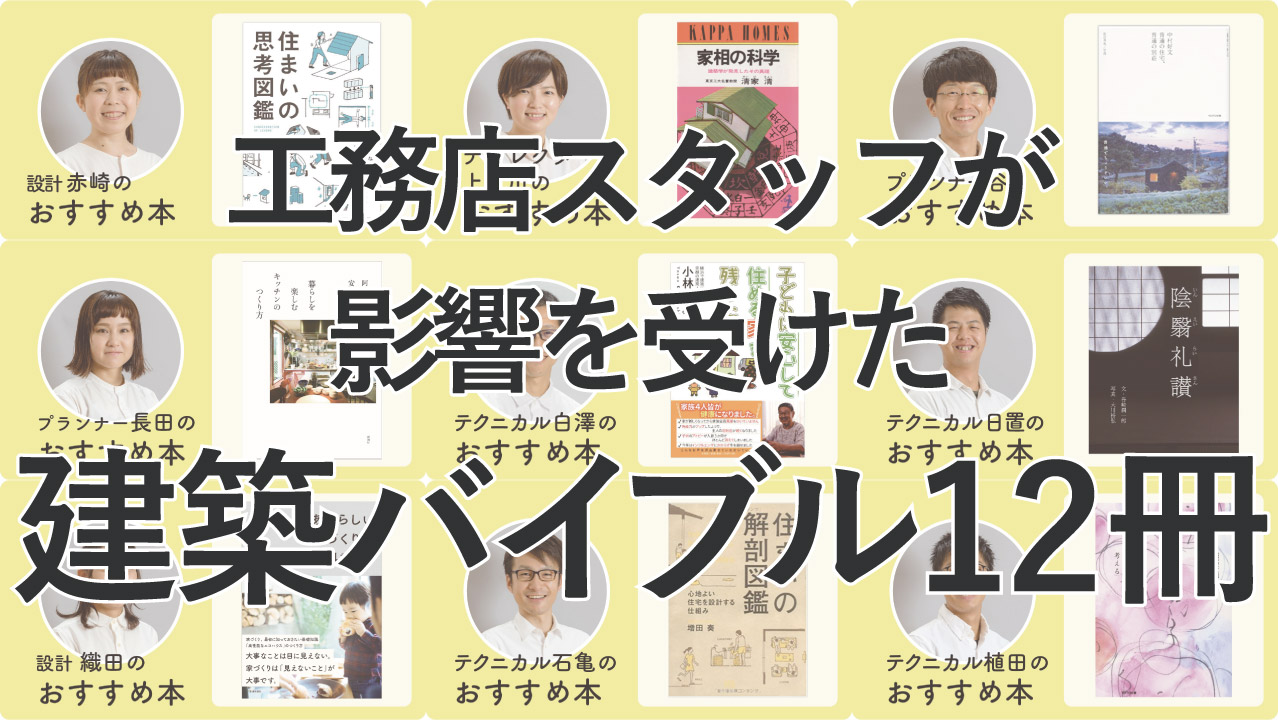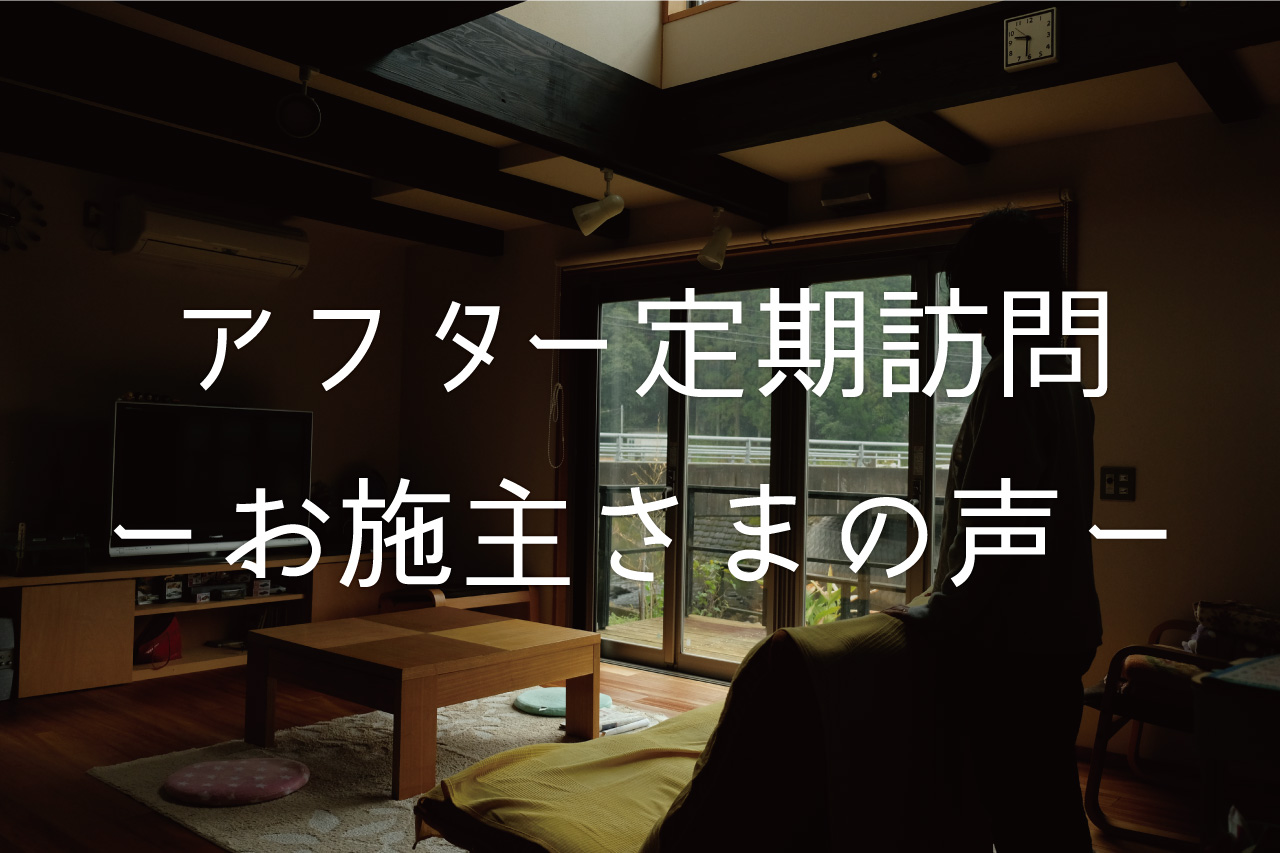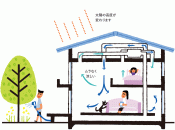ソファは空間のイメージを大きく左右する大物家具のひとつ。とくにリビングでの過ごしやすさ、快適性にも関わってくるので、家族のライフスタイルにぴったりのものを選びたいところです。
ソファというと、まずはデザインやカラー、素材(張り地)、サイズなどに目が行きがちですが、座り心地が決まるのは構造。実は内部構造でソファの価格に違いが出ることも多いんです。
さらに注目したいのが、ソファの座面の衝撃吸収の役割を果たす、クッション材。フェザーやウレタンなどの種類や質によって座り心地はもちろん、耐久性も大きく異なります。人気の無印良品でもフェザータイプのソファと、ウレタンタイプのソファが発売されていますが、どちらも好評の模様。今回は、ソファの素材をテーマにブログを展開いたします!
ソファの座面に使用されているクッション材には、どんな種類があるの?

ソファの座面の内部は、コイルスプリングやバネの上を衝撃吸収材としてクッション材が覆っています。(部位によって使い分けられていることも)。座面に使用されている主なクッション材「フェザー」と「ウレタン」についてご紹介します。
続きを読む